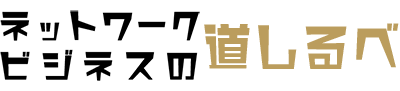ネットワークビジネスって、なんだか怪しいイメージがあるけど、本当はどうなんだろう?
マルチ商法やネズミ講って名前もよく聞くけど、それらとはどう違うの?
このような疑問を抱えたことはありませんか?
ネットワークビジネスという言葉に、なんとなく怪しい印象を持っている人は多いかもしれません。
しかし、実際の仕組みやルールを知れば、その誤解が解け、新しい可能性が見えてくるはずです。
この記事では、ネットワークビジネス初心者でも分かりやすいように、そのシステムや仕組みを解説します。
また、マルチ商法やネズミ講との違いを詳しく説明し、安心して検討できる情報を提供します。
副業や新しいキャリアを考えている方、将来に向けて何か始めたい方の疑問や不安に寄り添いながら、現実的な選択肢としてネットワークビジネスを理解できる内容になっています。
ぜひ最後まで読んで、理解を深めてください。
けど、その辺りがしっかり理解できれば不安はなくなりましたね。
この記事で分かるポイント
- ネットワークビジネス(MLM)の基本的な仕組み
- マルチ商法やネズミ講との違いをしっかり理解できる
- ネットワークビジネスを始める際のリスクと可能性が分かる
- 自分に合った副業として検討するためのヒントが得られる
ネットワークビジネス(MLM)とはどんなビジネスか?

ネットワークビジネス(MLM)とは、ビジネス参加者が商品を販売したり、他の参加者を勧誘することで利益を得るビジネスです。
簡単に言うと「商品を使って良さを広める人が、広めた分だけ報酬をもらえる仕組み」となります。
自分が勧誘した会員から新たな商品の流通(販売)が生まれたり、勧誘した会員がさらに新規会員を加入できた場合には、上位者(勧誘した会員の上の人)に対しても報酬やボーナスが発生する場合もあります。
このように、人から人へと製品流通を拡大していくビジネスモデルのことを、ネットワークビジネスといい、別名では『MLM(マルチレベルマーケティング)』や『マルチビジネス』や『マルチ商法』とも言います。
日本ではもともと「マルチ商法」という言葉で浸透してましたが、悪いイメージがついてきたことから「ネットワークビジネス」や「MLM」などの呼び方に変わったものだと思います。
ネットワークビジネスは日本では特定商取引法第33条において「連鎖販売取引」として規定されており、法律においては合法なビジネスになります。
連鎖販売取引の定義としては、以下の内容に該当するビジネスモデルになります。
特定商取引法は、「連鎖販売業」を次のように規定しています。
- 物品(施設を利用し又は役務の提供を受ける権利を含む。)の販売(又は役務の提供など)の事業であって
- 再販売、受託販売若しくは販売のあっせん(又は同種役務の提供若しくは役務提供のあっせん)をする者を
- 特定利益が得られると誘引し
- 特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの
具体的には、「この会に入会すると売値の3割引で商品を買えるので、他人を誘ってその人に売れば儲かります」とか「他の人を勧誘して入会させると1万円の紹介料がもらえます」などと言って人々を勧誘し(このような利益を「特定利益」といいます)、取引を行うための条件として、1円以上の負担をさせる(この負担を「特定負担」といいます。)場合であれば「連鎖販売取引」に該当します。
実態はもっと複雑で多様な契約形態をとっているものも多くありますが、入会金、保証金、サンプル商品、商品などの名目を問わず、取引を行うために何らかの金銭負担があるものは全て「連鎖販売取引」に該当します。引用:特定商取引法ガイド
物品の販売をする人を勧誘する行為により、金銭の負担(特定負担)があるビジネスモデルの場合、連鎖販売取引に該当するネットワークビジネス(MLM)になります。
例えば、金融投資・仮想通貨・不動産投資などは物品の販売がないので、違法ということです。
ネットワークビジネスで報酬が生まれる仕組みは流通形態にある
ネットワークビジネス(MLM)ではどのように報酬が生まれるのか、その仕組みについて一般的な製品販売との違いと比べて説明します。
一般的な会社の製品販売と流通
普段、私たちはスーパーやコンビニ、Amazonや楽天市場といったショッピングサイトで買い物をします。
ですが、その商品が手元に届くまでには、さまざまな仕組みが関わっていることをご存じでしょうか?
例えば、会社が開発した製品を小売店の店頭に並べるには、卸売業者を通して仕入れるのが一般的です。
しかし、商品がただ並んでいるだけでは、消費者に認知されず売れにくいですよね。
そのため、会社はテレビCMや雑誌・ネット広告を使って製品をアピールします。
特に、芸能人を起用したCMは商品の知名度を一気に高める効果がありますが、その広告宣伝費として非常に大きなコストがかっている場合もあります。
図で表すと以下のようになります。

このように、製品が消費者の手に届くまでには、卸売業者の手数料、広告宣伝費、輸送費など多くのコストがかかります。
さらに、小売店側も売れることを見込んで在庫を抱えますが、予測が外れて売れ残れば不良在庫となるリスクもあるんですね。
こうしたコストやリスクを考慮した上で、製品の価格が設定されているのが、一般的な販売・流通の仕組みなのです。
ネットワークビジネス(MLM)での製品販売と流通
次はネットワークビジネス(MLM)においての販売、流通について説明します。
ネットワークビジネス(MLM)はビジネス会員が製品を周りの人に伝え広めていく、いわゆる口コミによる手法で販売、流通の連鎖を生み出します。
そのため、広告や宣伝、CMなどにかかるコストがかかりません。

また、製品は会社から会員へ直接届くため、卸売業者を挟んだり小売店で販売してもらうためのコストも必要としません。
基本的には会員の必要な注文数のみを生産、販売となりますので、不要な在庫を生産する必要もないため、それらを踏まえた価格設定とすることもなくなります。
このように、一般的な販売、流通方法とではコストや価格設定の部分で大きな違いがあります。
浮いたコストを報酬として会員に還元される仕組みがある
一般的な製品販売の仕組みとネットワークビジネス(MLM)では、コストや価格設定に大きな違いがあります。
ネットワークビジネスでは、広告費や流通コストといった中間的な費用を削減できるため、浮いた分のコストを他に活用できるのが特徴です。
具体的には、削減されたコストを製品の開発や研究に充てたり、製品価格を抑えることが可能になります。そしてもうひとつの大きな特徴が、この浮いたコストを製品を広めたり、新しい会員を紹介してくれる人への報酬として還元する仕組みです。
ただし、報酬プランやボーナスの設計はネットワークビジネスの会社ごとに異なります。
それぞれの会社の特徴や仕組みを理解することが、ネットワークビジネスを成功させるポイントですね。
詳細については、各ネットワークビジネスの記事や報酬プランも参考にしてみてください。
ネットワークビジネス(MLM)とネズミ講の違いとは?

世の中では「ネットワークビジネス(MLM)=ネズミ講」と勘違いし、悪いイメージを持たれている人も多くいます。
しかし、ネットワークビジネスとネズミ講とでは以下のように違いがあります
| 名称 (別名) | ネットワークビジネス (MLM・マルチ商法・マルチビジネス) | ネズミ講 (マルチまがい商法・無限連鎖講・ピラミッド・スキーム) |
|---|---|---|
| 法律上 | 合法 | 違法 |
| 商品の流通 | ある | ない |
| 入会金や負担額 | 安価なもの〜高額なものまで | 高額 |
| 報酬構造 | 開始時期に関係しない | 早く始めた人が優位 |
大きな違いのポイントとしては以下の3つになります。
- 法律での位置づけが違う:
ネットワークビジネスは合法だけどネズミ講は違法 - 製品やサービスの有無:
ネットワークビジネスは製品やサービスがあるが、ネズミ講は金銭のやり取りのみ - 持続可能性と公平性:
ネットワークビジネスは持続可能であるが、ネズミ講は必ず破綻する
ここからは、上記の重要なポイントを詳しく説明していきます。
違い①:法律の違い”ネズミ講は違法で犯罪”で”ネットワークビジネスは合法”
ネットワークビジネス(MLM)とネズミ講とでは、法律の取り扱いに大きな違いがあります。
ネットワークビジネス(MLM)は特定商取引法第33条にて「連鎖販売取引」として規定されており、そのビジネスモデルが正しく認められています。
連鎖販売取引は、1976年に「訪問販売等に関する法律」により初めて規定され、2001年に現在の「特定商取引法」に改称されてからも、改正を経ながら変わらず取り扱われいます。
それが理由で 「ネットワークビジネス = 違法で犯罪」というイメージを持たれていますが、実際のところネトワークビジネス自体はクリーンなビジネスです。
嘘の情報を言って自分のビジネスに引っ張ろうとする人は信用できませんし、詐欺師が多いので気をつけましょう。
一方、ネズミ講は「無限連鎖講の防止に関する法律(ネズミ講防止法)」において違法行為として禁止されています。
「無限連鎖講を防止に関する法律」は1979年に施行されており、近い時期に制定された「訪問販売等に関する法律」も加え、ネットワークビジネス(MLM)とネズミ講とを明確に区別されることになりました。
後で詳しく説明しますが、なぜネズミ講が違法となっているのかというと、「終局において破綻すべき性質のもの」という、簡単に言えば“必ず最後は破綻する仕組み”だからです。
法律で正しく区別されることになった背景についてまとめた記事も作成していますので、参考にしてみてください。
違い②:製品の有無”ネットワークビジネスには製品やサービスがある”が”ネズミ講はない”
ネットワークビジネスもネズミ講も似たようなビジネスモデルですが、製品の取り扱い(製品の有無)に違いがあります。
ネットワークビジネス(MLM)では製品やサービスがあり、それらの売上が会社の収益や会員の報酬となります。
売上のうち、会社の利益と会員への報酬との分配が決まっているので、流通(会員の製品購入)が行われている限り破綻することはありません。
一方で、ネズミ講は製品やサービスが存在せず、会員の紹介料だけが収益源となります。
製品やサービスが存在しないので、新しい会員を勧誘し続けなければ仕組みが維持できず、最終的には破綻することが避けられません。
違い③:持続可能性と公平性”報酬範囲の制限の有無”
ネズミ講は下位の会員から出資金や会費などの金銭を徴収し、上位会員(先に登録した人)へ分配するシステムとなっています。
上位会員は下位会員からの分配金を受け取れますが、下位会員(新規参加者)は同じように出資してくれる人を勧誘しなければ報酬がもらえません。
しかし、実際のところ人口は有限であるため、無制限に組織が成長し続けることはなく、最後には破綻するシステムです。
他にもネズミ講は、報酬を得られるかどうかが参加時期や勧誘力に依存するため、公平性に欠けます。
特に、後から参加した人が損をする仕組みになっており、不平等です。
一方、ネットワークビジネス(MLM)では報酬を得られる範囲に制限があるのが特徴です。
各企業の報酬プランに違いはありますが、報酬の対象となる段数や人数に対して制限がかかっているのがほとんどです。
そのため、後からネットワークビジネス(MLM)へ参加した人でも、場合によっては「上位会員よりも多くの報酬が得られる」ということもあります。
なかには上位者のグループから独立する「ブレイクアウェイ」という報酬プランもあります。
騙されずにネットワークビジネス(MLM)を始めよう!

ここまでネットワークビジネス(MLM)とネズミ講の違いを解説してきました。
ポイントをまとめると以下になります。
ねずみ講とネットワークビジネスの違いまとめ
- ネットワークビジネスは法律で認められているがネズミ講は違法
- ネットワークビジネスは商品やサービスがあるがネズミ講にはない
- ネットワークビジネスは持続可能だけどネズミ講は必ず破綻する
ネットワークビジネスはネズミ講と混同されてしまいますが、実際のところ法律で正しく認められているビジネススタイルです。
これからネットワークビジネスを始めようと考えていたり、今現在勧誘を受けているかもしれませんが、両者の違いが理解できていれば怪しいビジネスやネズミ講(詐欺)に引っ掛かるリスクは減るはずです。
日本にはネットワークビジネスの会社が多くありますので、正しいネットワークビジネスの会社を選択しましょう!